防衛大学校への入学を決めた原さん。しかし、自衛隊での経験を経て、彼がたどり着いたのはまったく異なる道でした。防衛大での驚き、海上自衛隊での気づき、そして日本文化への思いが彼を突き動かし、ゼロからの起業へとつながっていきます。
京都の呉服業界に飛び込み、苦難の連続だった創業期をどう乗り越えたのか?波乱万丈な軌跡を、ぜひご覧ください。
【プロフィール】
原 巨樹 :大分県出身の実業家で、「京ごふく二十八」の代表を務める。防衛大学校を卒業後、海上自衛隊に入隊。幹部候補生学校(江田島)を修了し、護衛艦「やまゆき」に勤務。その後、2005年に退職し飲食店や呉服店を経て、着物文化への深い関心から、2014年に「京ごふく二十八」を創業し、伝統工芸の継承と発展に尽力している。
古川勇気:2024年7月にBallista入社。8月からスタートした「Catapult」を担当。防衛大卒業後、入社試験時の適性検査を販売する企業で営業職などを経験。人材獲得や入社後のミスマッチに課題のある会社の内定率向上や離職率低下に貢献した。
自衛隊(防衛大)に入った理由
古川:まず、防衛大に入校されたきっかけや経緯を教えてください。
原:高校3年生の10月頃に、防衛大学校の試験があり、学校の先生から「模試みたいなものだから全員受けなさい」と言われたんです。それで、ほとんどの生徒が受けに行ったと思いますし、私もその中の一人でした。実は元々建築学科に進みたかったのですが、父親が建築業界にいたため、「建築業界は大変だから」と反対され、防衛大を勧められました。私が、「防衛大学校に行けば厳しい環境についていけないかもしれない」と弱音を吐くと、「そんなことじゃ建築業界も無理だ」と言われ悔しい思いをしました。それと同時に反骨精神が働き「防衛大で自分を鍛えてやる!」と、一転防衛大に入校することを決めました。
防衛大での驚きと学び
古川:防衛大に入ってみて驚いたことはありましたか?
原:よくわからず防衛大に入ってしまったので、驚きの連続でした。制服や作業服の着方だけでも衝撃を感じたことを覚えています(笑)。ですが逆に先入観がなかったおかげで、出てくる課題に対して素直に順応することができました。
古川:防衛大の環境への適性をお持ちだったんですね。
原:そうですね。8割程度はなんでも器用にこなせました。自分で言うのもなんですが、旧海軍でいうところの「スマートで、目先が利いて、几帳面、負けじ魂、これぞ船乗り」というタイプでしたね。 ですが、根本的な部分では、自衛隊という大きな組織の中で働いていくことに対しての違和感を持っていました。組織の中で上司に評価される立場であり続けることや、本番がなく訓練のための訓練で多くの時間を使うことなどに対しての違和感です。ですので、防衛大にいるときから自分が自衛官をずっと続けていくことに対して疑問を持っていました。
海上自衛隊での世界との接点
古川:原さんは防衛大を卒業後、海上自衛隊に入隊されています。海上自衛隊ではどんなことが印象的でしたか?
原:海上自衛隊の遠洋航海で南米を訪れたとき、各国のレセプションパーティーに参加する機会がありました。そこで強く感じたのは、文化の持つ力です。どの国も自国の文化を誇りに思い、それを堂々と披露していました。現地の人たちが、自分たちの伝統を自信満々に紹介する姿を見て、日本はどうだろうと考えたのです。 いざ自身を振り返ると、自分ひとりで着物も着られないし、日本文化らしいものが身についているわけでもない。それが悔しくて仕方なかったですね。明治以降の西洋化や戦後の無国籍化を思うと、日本人としての誇りをもっと持つべきじゃないかと強く感じました。
また、もう一つ印象的だったのは、軍服に対する世界の見方の違いです。日本では制服姿で東京を歩くと、若者から指をさされて笑われることもありました。ですが、南米のスラム街を歩いたときは、年配の方が年下の私に敬語で話しかけてくれました。軍の制服は敬意を持って接するべきものだという意識が、海外では当たり前なのです。この経験から、日本人ももっと自国の文化や伝統に誇りを持つべきだと痛感しました。
退官、そして民間での就業
古川:その体験が現在の事業に活きているわけですね。海上自衛隊を辞めてからは民間企業でどのような仕事をされていたのですか?
原:そうですね。あの経験がなければ、今の仕事をしていなかったかもしれません。日本の文化に対する意識が大きく変わるきっかけになりました。 海上自衛隊を辞めた後は、まず民間企業に勤めました。とはいえ、最初から着物に関わる仕事をしていたわけではなく、知り合いの社長さんのもと、飲食店で働きはじめました。アルバイトもしたことがなく、民間での仕事は初めてでしたが、朝から晩まで必死に働きました。そこで働きながら、プライベートでは着物を買ったり職人さんに会いに行ったりして、どんどん着物への興味関心が強くなりました。
その中で知ったのですが、職人さんたちがどれだけ素晴らしいものを作っても、呉服業界の流通の仕組みが不透明で、職人に正当な報酬が入らない現状がありました。そこで、『この業界を内側から知るために、まずは呉服店で働こう』と決意し、東京の呉服店に就職しました。最初の面接で『将来は独立します』と伝えたうえで採用していただき、そこで5年間、販売や接客を学びながら業界の仕組みを徹底的に研究しました。 そして、他のアルバイトを掛け持ちして貯めた50万円を元手に起業しました。
志を持って起業するも苦労の嵐
古川:呉服店で修業してから、起業されたのですね。起業後は最初からスムーズにいきましたか?
原:最初から順調だったわけじゃありません。京都は老舗がものすごく強い街で、新しく呉服屋を始めるなんて無謀だと言われましたし、実際に業界の抵抗もありました。独立したばかりの頃は信頼もないので、職人さんたちに『本当に仕事を任せて大丈夫なのか?』と疑われることもありました。 あと、とにかくお金がなかったですね。最初に借りたオフィスなんて、家賃は月1万5000円でしたから、そこからのスタートです。 事業を始めた頃は、京都から夜行バスに乗って東京に行っていました。年間70日から80日程度は夜行バスで寝ていたんじゃないでしょうか。東京に着いて泊まるのは、南千住のドヤ街。日雇い労働の方々が泊まるような場所で、宿泊費は3000円くらいだったかな……「あしたのジョー」に出てくるような場所です。 そんなところに泊まりながらも、仕事では裕福なお客様の家に着物を持って訪問する、みたいなことをやっていました。本当に貧乏エピソードはいくらでもありますよ。(笑)
古川:大変な苦労を乗り越えて今があるのですね。どうしてそこまで頑張れたのですか?
原:人間は誰しも人生を“体験”として味わっている感覚を持っていると思います。「なんて不幸なんだ」と落ち込むような出来事が多かったとしても、そう思わないためには、私は体力と知性が必要だと思っています。 知識として、昔の人たちがどのよう頑張って、今の日本を作ってくれたかを知ることも大事ですし、そういった歴史になぞらえて自分を見つめ直すことも多いです。 私は今でもお金がないとか、色々なことで苦労してると思うのですが、それでも「いやぁ、味わい深い人生だな」と思います。そう思うようにしていますし、実際にそうだとも思っています。
もう一つ、私が大事にしている考え方として、「志」があります。「志」が何かという話になりますが、たとえば私の場合は、「日本がこんなふうになってほしい」という思いが根底にあります。 たとえば、今ある呉服業者が、ラグジュアリーブランドのようになり、世界中で山ほど着物が売れていく。そして、職人さんたちへ次から次へと仕事が舞い込み、「もう若い人材を雇わなくては仕事が回らない!」という状況になり、更に業界が活性化していく。そして、世界から「やはり日本はすごい国だ」と尊敬される。そんな未来が実現できるなら、私はもう今日死んでもいいなと思うんです。 仕事をするということは、結局、自分の時間や命を使うわけですから、どうせならそんな「志」に根付いた仕事をしたいいですよね。 そういった「志」があるからこそ、何度断られても、ひたすら現場に足を運んで、職人さんの技術を学び、彼らの言葉に耳を傾けることができました。そうして信頼を積み重ねるうちに、京都でもトップクラスの職人さんたちと一緒に仕事ができるようになりました。起業から数年が経ち、今では京都でも一目置かれる呉服屋になったと自負しています。
古川:志に根付いた仕事をしている人はかっこいいですよね。原さんがイキイキと輝かれているわけが少しわかりました。
今後の目標:新しい和装を創る
古川:原さんは新しいアパレルブランドを立ち上げられていますが、今後の目標はありますか?
原:直近で言うと、とにかくそのブランドを大きくすることが目標で、そればかり考えています。今までの高級呉服ももちろん続けますが、こちらは地道に成長していくしかありません。 ただ、アパレルの方は実際にやってみるとすごくニーズもありそうですし、規模拡大の可能性を秘めているので、現在はそちらに特に力を入れています。
古川:どのようなアパレルブランドなのでしょうか?
原:新しい和装を作りたいと思っています。「着物」と聞くと多くの方が思い浮かべるのは、いわゆる伝統的な和装だと思います。しかし、もし明治時代に入った後も開国せずに鎖国が続いていたら、もっと動きやすい着物が発展していたんじゃないかと思うんです。 実際に江戸時代の職人さんが着ていた服は今でいうズボンのようなものだったり、袖も大きな四角い形ではなくなく実用的な形だったんです。ですから、私が150年分の進化を一気にさせ、「これが新しい和服です」という形で提案していきたい。それが私のブランドの一番のコンセプトですね。 日本の方にももちろん着てほしいですし、世界の方にも届けたい。そんなブランドです。
古川:着物の定義を広げていくようなブランドですね。
原:そうですね。そこが本当に面白いポイントで、「何が着物なのか?」というところから考えなくてはいけないんです。 例えば、今私たちが「着物」と呼んでいるものと、平安時代の貴族が着ていたものは全然違いますよね。鎌倉時代の武士の服もまた違います。しかし、どれも「日本の服」だったわけです。更に遡れば、ヤマトタケルノミコトなどの神話の時代の衣服だってあります。 今の日本人はある一定のものだけを、「これが着物だ」と思い込んでいるんですよね。 洋服の定義も同じで、専門の人に聞いても即答できないんです。色々な要素が混ざりすぎていて、「何が洋服か?」と聞かれると、意外と答えにくい。 私は呉服屋をやっているぐらい着物を愛していますし、日本が大好きですから、そんな私が作る服は総じて「着物」なんです。私が着物だと思って作るのですから、それは「着物」だという主張ですね。
古川:なるほど。それは原さんだからこそ言えることですね。
原:そうなんです。私は0から呉服屋を立ち上げて、10年やってきました。今、京都の呉服屋としては一番だと思っていますし、日本でも、世界でも一番だと思い仕事をしています。 だからこそ、新しい着物を作ることができる。普通の呉服業者は、なぜ着物が売れないのかや、更に売上を伸ばす方法ばかり考えています。 ですが私は「世界で自分しかできないことをやる」という想いを持って仕事をしていますし、今のブランドのコンセプトは、自分にしかできないと思っています。 呉服屋を始めた時も「私より呉服屋になりたい人は、世界に一人もいない」と思い立ち上げました。私がやらなかったら、誰もやらない。それが今の呉服業界の現状なのです。 だからこそ、「私がやるしかない」という使命感を持ち仕事に取り組んでいます。それが私の「志」なんです。
キャリアに関するアドバイス
古川:最後に今後のキャリアに悩む自衛隊出身者にアドバイスをお願いします。
原:仕事に悩んでいる方は、何を優先するかで迷うことが多いと思います。しかし、「自分の人生をかけてやりたいこと」を見つけることが重要だと思います。
古川:やりたいことを見つけるのは誰しも難しいですよね。
原: 見つけられる人とそうでない人がいると思います。特に大人になると難しくなる。 ですが、小さい頃は、目の前にやりたいことがあるじゃないですか。ゲームしたいとか、公園行きたいとか。 それが小学校に入った途端、「勉強ができるやつが一番偉い」と価値観を植え付けられるんです。そして「いい中学、いい高校、いい大学、いい会社に入るのがゴール」、そんな考え方が刷り込まれる。その価値観に縛られ10年、20年と経つうちに、「自分は何が好きだったんだろう?」とわからなくなってしまう。本当にやりたいことを見つけるのが難しくなるんですよね。 ただ、もし自分の本当にやりたいことを見つけることができば、同じ能力でも全く違う力が出せると思うんです。嫌な仕事をしていたら100の力が50とか30になってします。ですが、「これだ!」と思える仕事ならば100の力が200にも300にもなる。そういった気持ちがすごく大事だと思います。 やはり大事なのは「自分に合った志を見つけること」ですね。
最後に
自衛隊出身者専門のキャリア形成サポート「Catapult」では、自衛隊経験のあるキャリアパートナーが伴走し、あなたのやりたいこと探しからお手伝いいたします。今の生き方や働き方に違和感を感じられている方は、まずは気軽にご相談ください。
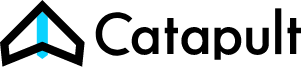










コメント